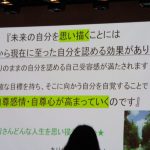先週に引き続き、9月14日(土)は三国サンセットビーチの清掃を行いました。
企業や団体、ホームページなどを見て申し込まれた方、合わせて106名がご参加くださり、さわやかな秋晴れの中清掃活動を行いました。
たばこの吸殻や、ペットボトルに空き缶など、まだまだゴミはおちており、約30分で燃えるゴミが45袋、燃えないゴミが15袋にもなりました。
今年度も多くの方にご協力いただき、無事海岸クリーンアップの活動を終えることができました。
私達に多くの恵みを与えてくれるふるさとの海に、少しでも恩返しができたと思います。季節は本格的な秋へと移っていきますが、1年通して美しい環境を守り未来へ引き継いでいくために、ボランティア活動の輪を広げていきます。
ご参加の皆様、ありがとうございました。
| 参加人数 | 企業・団体数 | 燃えるごみ(袋) | 燃えないごみ(袋) | |
| 9月7日 鷹巣海岸 | 183 | 6 | 10 | 5 |
| 9月14日 三国 | 106 | 7 | 45 | 15 |
 |
 |
 |